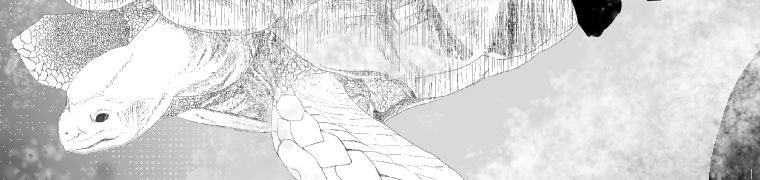01.ポスティングサービスに関するお願い
現在時刻は一般的なお昼時である。仕事中の人々だとて一息つくであろう時間帯、とあるマンションの一室は重苦しい空気に包まれていた。
――いらっしゃいませはもう言った。どんな用件かと聞くのは憚られる。そんなことを言えば目の前の異国人に冷笑される。いやいや、冷ややかにでも笑われれば御の字だ。無言のまま睨まれる。きっとそうだろう。
あまねはちらりちらりと彼を見て、最初の一言をどう切り出すかと考えていた。細められた目が彼女を通り越した先を見ていることに気が付くまでは。
「あの、もしかしてお昼ごはん、まだ、ですか?」
彼の視線の先にあるものは鍋である。中身は、未完成のままで放置された茸のクリームリゾットだ。
「素人作なので味の保障はできませんが、それでもよろしければ」
どぞ、と、質問を投げ掛けたまま返答を待たずあまねが彼に背を向ける。彼の反応を待つのは大層な労力が要るような気がしたし、それを得る前に自身の生命値がなくなるような気もしたからだ。
キッチンの奥へと向かったあまねは冷蔵庫からパルメザンチーズとバターを取り出した。同時に常備している水出しコーヒーのボトルも出し、抽出が済んでいることを確認した。それから火を止めていた鍋を再加熱し、カウンターに用意していた食器をもう一揃い追加する。リゾットを木べらで大きく混ぜてからもう一度味見をし、少し顔を顰めて「せっかくのアルデンテが」と呟く。そうしてリゾットが温まるまでの間、彼女は初めて、彼女の城たるこの部屋のこの造りに不満を感じた。
あまねは別段、自炊やそのほかの水仕事に思い入れがあるわけではない。新居のキッチンに求めていたことは広めのシンク、くらいである。この物件の間取りを見たとき、また実際に内見をしたときも「ああ、対面式なんだ」という程度の感想しか持たなかった。ただ、生活を始めてみて気付いた、キッチンの中が見えないことの――つまりは掃除に手を抜いても許されることの――ありがたさにどっぷりと浸っていた彼女は、『対面式とはなんぞや』ということをすっかり失念していた。
あまねと鍋に注がれる彼の視線は鋭い。彼は先日と同じく顎の下で手を組んでおり、やはり無言である。その姿をあまねは努めて視界から外し、準備したロングタイプのグラスふたつの内、ひとつに氷を入れコーヒーを注いだ。シルバートレイにシルバーカトラリー、などという上品なものは彼女の部屋にない。ミルクポーションもガムシロップもない。しかし「どうせ飲まないんだろうし」、これで良いだろうと手掴みでグラスを持ち彼に渡す。
「どぞ。ブラックですが」
「――ブラック」
「甘いのがお好きでしたかごめんなさい次はガムシロとミルク用意しときます」
低い声色にぺこぺこと頭を下げて、あまねは早足でキッチンの中に戻る。タイミング良くぽこぽこと音を立てていたそれを器に軽く盛り、木のスプーンと一緒にテーブルへ並べる。
「どう、ぞ、あれ?」
次は自分の分、と考えて半回転したあまねの体が止まる。グラスの中の魅惑の液体が七割方減っている。
「何だ」
「ブラックコーヒーは、嫌いかと」
眉間に皺を寄せた彼があまねを見る。鼻で笑うような仕草をした彼は、すぐに興味の対象をリゾットとスプーンに移す。しばらくそのまま動かずにいた彼が、腕を胸下で組み直し、ちらとあまねを見る。
「お前の分は無いのか」
「え、あ、はいあります。持ってきますのでどうぞ先に召し上がってて下さい」
急げ、と言外に伝えられた心持ちであまねが駆け出す。
「――木製の、食器か」
背後で落とされた彼の呟きは、これから始まる素敵な昼食会兼意見交換会の幸先を暗示している。そんなこれっぽっちも楽しくない予感にあまねはぶるりと震え、たまらずふひ、と息を吐き出した。
* * *
異国の聖人方が集いたもうた最後の晩餐だとて、恐らくこの場よりは盛り上がっていたのだろう。そう不敬な想像をしたくなるほど空気は重い。
彼はあまねがどれだけ勧めても彼女より先に匙を取ろうとしなかった。素晴らしいレディーファースト精神をお持ちですね、とごますりをした彼女に向けられたのは失笑、それのみである。しかし、彼女が口を付けてからややあって始まった彼の食べっぷりは素晴らしかった。彼に視線で三度目のおかわりを要求されたとき、匙の進まないリゾットに四苦八苦していたあまねは立ち上がり、鍋を引っ掴み押し付けて笑顔で伝えた。
「セルフサービスでお願いします」
そんな経緯があってテーブルの中央に置かれた鍋は現在彼寄りになっており、中身は空である。コーヒーも一度追加で注いだが、これは絶対に冷やしておかねばなりません、とあまねが態度で示した結果、無事冷蔵庫の中にある。急に立ち上がった彼がキッチンに向かい、勝手に冷蔵庫から出して注いでいる今の限りでは、中身はそうとも言えないけれども。
「何故、これから出さない」
左手にグラスを持った彼が、これだ、と、細い顎で冷蔵庫を指し示す。
「……アイスコーヒーは、当然ですけど冷やしておいたほうが美味しいでしょ? それに」
「何だ」
「劣化が、早まるので」
成程、と彼が頷き、あまねの前に座る。「お前は」
「この飲み物に思い入れがあるようだな」
「は、あ。まあ、それなりに」
何でまたそんなことを聞くのかと、あまねは胡乱げに彼を見る。確かに彼女はコーヒーが好きだ。本当の通のようにどこどこ産の豆じゃないとだめだとか、インスタントは認めないとかそういうこだわりはない。牛乳も砂糖も気分次第で入れる。ただ、水出しコーヒーが作り易いポットやコーヒーメーカー、ミルを購入する程度には好きだった。
「管理人さんも、お好きですか?」
「ああ。温かい方が良いが」
「ホット派でしたか。……お腹がたぷんたぷんじゃなければ淹れますけど」
鍋敷き代わりにされていたチラシを手に、彼が微かに頷く。あまねは「では」と頷き返し準備と片付けに取り掛かる。彼女の腹は重くなっていたけれど、キッチンへ向かう足取りは軽い。彼女がコーヒーの好みを訊ねれば、彼からは短くも刺々しさのない答えが返ってくる。
沈黙の食卓から救ってくれてありがとうコーヒー様、とあまねは呟き、「何か言ったか」と顔を上げた彼に首を振り笑顔で返す。
「コーヒーって偉大だな、と」
ふ、と彼の口元が緩んだ。「笑えたのか、お前は」
「それ、は……貴方にそのままお返しします」
あまねがくそうこの美形め、と上目遣いに睨み上げれば、彼は小さく声を上げて笑った。「お前は面白いな、アマネ」
さて。私に進言したいことがあるならば聞くが。彼からそう切り出されたあまねは大きく頷き、ええと、と唾を飲み込む。
「最近、困ったことがありまして」
あまねが切り出すと、彼が長い足を組み「困ったこと」と目を細める。
「はい。ここって、不動産屋さんに聞いていたとおり、外部からの人間をシャットアウトする造りですよね? 確かに入居してすぐは新聞の勧誘やらなんやらが全く来なかったんですよ。それがここ二日続けて、室内ポストにチラシが入ってたんです。なんでかなーって疑問だったんですけど、理由が今日分かりまして」
「内部の者か」
「え、凄い。そうですそうです! たぶんここに住んでる人だと思うんです。これまでにも何回かすれ違ったことがありますし、手に紙の束を持ってましたし」
「容貌は」
「ええと、縦にも横にもかなり大柄な男性です。長めのパンチパーマが印象的な。服装はいつも……怖い職業の方々が着るような派手目のアレな感じで」
「パンチパーマ」
「はい。えーと、ちょっとお待ち下さい」
あまねがサブPCを手元に引き寄せる。かたかたとキーボードを叩く彼女の目的は、犯人と思しき男に似た髪型の画像検索だ。
幸いなことに画像は豊富に出てきた。「こんな感じです」と言いながら限界までPCを開いたあまねが、検索トップの画像を画面いっぱいに表示する。
「顔は――正直良く覚えていないんですけど、髪型はまさにこんな感じでした」
どうですか入居者にこんな方はいませんかねああいえもちろん個人情報ですから無理にとは言いませんけれどもふひひ。あまねはそうワンブレスで伝え、窺うように顔を上げた。
向かい合わせで座る彼は、眉を顰め軽く身を乗り出して画面を注視している様子である。てっきり鼻で笑われる程度だろうと想像していたあまねにとっては喜ばしいことだ。だから、それを見た彼女が今後の展開に心躍らせたことは仕方のないことであり、
「――狸め。下らんことを」
極低温の極々低音でそう呟かれた彼女が、不整脈で心を騒がせたのもやはり仕方のないことである。何かのゲームのキャラクターのような、映画のワンシーンのような、国家的犯罪を目の当たりにした権力者の如き彼にあまねが慌てて言い募る。「あの、私は宗教とか新聞とかの勧誘さえなければそれで十分でして――」
「アマネ」
小さく、抑揚を抑えた声で彼に名前を呼ばれ言葉が止まる。
「今は価値のない紙切れが送り付けられるだけだとして、だ。今後もそうであるとは限らない」
「は、あ。でも、どうしてもノルマ達成しなきゃいけなかったとか、のっぴきならない事情があったのかもしれないですし」
「ここに来ると決めたのは誰だ」
「は? え、そりゃもちろん入居者各位でしょうけど」
「その際、契約は遵守すべきと伝えられなかったか」
「確かに、従わない場合は強制退去もありますよとは伺っておりますけれども」
「では何故、従わない」
「ですから、何か事情があったんじゃないかと」
あまねは、自分がいつの間にやらポスティングおじさん(仮名)を庇う立場になっていることに首を傾げつつもごもご喋り続けた。互いの問答は平行線を辿り、どちらからともなく会話が止む。一息吐こうとあまねが手にしたグラスは空で、彼の手にあるそれにも中身がない。彼女はキッチンに来た理由がホットコーヒーを淹れるためだったことをようやく思い出し、立ち話に悲鳴を上げている腰に手を当てながら準備に取り掛かった。
「契約は、お前達を縛る為のものではない」
マグカップを用意しようとしていたあまねの手が止まる。珍しく――といっても、彼女が彼を知ってまだ数時間程度にすぎないのだけれど――疲れた調子なのが面白く思えて、あまねは笑いながら答えた。
「わかってますよ。私が言いたいことを纏められなかったから、ぐだぐだになっちゃってごめんなさい……温かいコーヒー、飲みます?」
「ああ」
* * *
あまねは彼の頭を超えた先にある【14:36:15】という表示を確認した。来客中、むやみに時間を確認することはいかがなものかと思い、慌てて視線を外し居住まいを正した。彼は本日数杯目のコーヒーを堪能していたようで、そんな彼女の様子を気にしてはいない。
あまねの計算が正しければ、彼の訪問から2時間以上が経過している。仕事を忘れ、心身のリフレッシュに費やされるべき48時間の内2時間を割いた。
「ええと、失礼を承知でお訊ねしたいのですが」
「ああ」
「まさかとは思いますが、これと色違いのマグカップの行方をご存知では?」
「ああ。私室に置いてきた」
「やっぱりご存知じゃなか――って、え?」
「持って行くぞと言った筈だが」
宴もたけなわではございますがそろそろお開きとさせて頂きたいのですが。そう切り出すつもりで用意したマグカップはひとつである。その理由もまたひとつで、あまね愛用のマグカップが見当たらなかったためだ。「いつでもいいので返して下さい」そう力の抜けた声であまねが願うと彼が鷹揚に頷く。「器と共に返そう」
「は、あ? 器って」
「次回は」
他にも何か持って帰ったのか、と問い詰めようとしたあまねの声は、ポケットから何かを取り出した彼によって遮られた。彼はそれを一瞥すると後ろを向き、再びあまねの方へと向き直りながら告げた。
「340時間後だ」
「は……え? や、私としてはもう十分こちらの意見を伝えましたし、今のところ他に何も不満はございませんのでそう何度もお越し頂かなくとも」
「私は権利を行使する。お前は義務を果たせ」
「えええ……し、承知致しました……で、いつでしたっけ?」
どこの独裁者だアンタはと胸中で憤慨しつつ、それを悟られぬよう心を配ったあまねの言葉は彼にどう捉えられたのだろうか。急に立ち上がり、玄関へと歩き出した彼を追いながらあまねは考える。「持っていろ」と差し出されたマグカップを両手で持ち、あまねは更に考える。
靴紐を締め終えたらしい彼があまねに手を伸ばす。はい、と渡そうとしてふと思う。いやいやいやちょっとまて何かおかしくないか。
「あの、これ」
無いと困るんだけどマジで、と言いかけたあまねの手にマグカップが無い。
「は? あれ?」
「少し待て」
右手にマグカップを持った彼がドアから出て行き、直後ドアホンが鳴る。混乱したままドアを開いたあまねの前に何かが差し出される。さっさと受け取れと、そう言わんばかりにずいと掲げられたそれらをあまねが抱える。と、下から現れた彼の手が緩く振られて、そうしてドアが閉まる。
「だから……次って、結局いつなのよ」
両手でそれら――見慣れた皿と愛用のマグカップ、そして見慣れぬティーポットとその注ぎ口に差し込まれた花一輪と判読不能な横文字の書かれたカードと、これらを入れている籠である――を抱えたままあまねは呟く。
連休を心穏やかに過ごせる自信がこれっぽっちもない。ふひ、と笑い、あまねは深く項垂れた。
- [↑]
- │
- 次へ
大したおもてなしも できませんが
本編
00 義務と権利
01 ポスティングサービスに関するお願い
02 愛玩動物との生活
03 ゴミ問題について
04 騒音被害
05 チカン、ダメ、絶対
06 ポスティングサービスに関する疑問再び
07 義務の放棄と権利の失効
08 退去時は30日前までに不動産会社までお知らせ下さい
09 またその際ライフラインは退居後に停止することを推奨致します
10 大したおもてなしもできませんが
あちらの世界はというと